サッカーは「考えるスポーツ」とよく言われます。
走力やテクニックももちろん大切ですが、それ以上に一瞬の判断がプレーを左右するんですよね。
グラウンドで子どもたちを見ていると、
相手が近くにいるのに無理にドリブルして取られてしまう子や、
ゴール前なのに迷ってシュートを打てない子、
さらには試合中に止まって味方任せにしてしまう子もいます。
学校の勉強は得意でも、サッカーの場面になると急に考えることが止まってしまう――そんな姿を目にすることもあります。
親として見ていると、「あの場面、もう少し考えられると違ったプレーになったのかな」とつい思ってしまいます。
素人ながらですが、そんなことを考えてしまうんです🤔
子どもが考えるのが難しい理由は?🌀
- 考える時間を取る習慣がない
大人でもそうですが、子どもは特に「間」をとって考えるのが苦手です。すぐに反応してしまい、条件や結果を想像する前に動いてしまう。経験が少ないからこそ起こることなのかもしれません。 - 選択の経験が少ない
いつも反射的に動いてしまい、自分で「選んだ」という感覚を持つ機会が少ない。 - ルール理解が曖昧
サッカーの基本がわからないと、どう判断すればいいのか整理できない。 - 「考えてうまくいった!」という体験が足りない
考えることが成功につながると実感できないと、なかなか習慣にはならない。
サッカーを通して「考える力」を育てる工夫✨
これはあくまで「サカパパが見ていて思ったこと」ですが、例えばこんな工夫ができそうです。
1. 小さな選択から慣れていく
日常生活でも「どっちの靴下にする?」みたいな小さな二択を積み重ねる👟
2. 練習の中で選ばせる
1対1なら「ドリブルかパスか」、2対1なら「仕掛けるか出すか」。
そのあとに「なんでそうしたの?」と軽く聞くだけでも違うと思います。
3. 振り返りの声かけ
試合や練習のあとに「ほかに方法あったかな?」と聞いてみる。
正解かどうかよりも「考えてみること」自体に意味がある気がします🔍
本からの気づき📚
最近読んだ 高崎康嗣さんの『「自ら考える」子どもの育て方―世界で通用するサッカー選手育成を目指せ!』 では、キーワードとして 「どのように脳に刺激を与えるか」 が語られていました。
紹介されていた問いかけの例はとても印象的でした。
「なぜ今パスしたの?」
「天候はどうだった?」
「グラウンドの状況はどうだった?」
「味方のコンディションは?」
こうした質問を繰り返し投げかけることで、子どもの脳に刺激を与え、「考える」スイッチが入るのだそうです。
考える習慣は一度身につけば一生の財産ですが、そのためには「問いかける」「振り返る」といった日常の小さな積み重ねが大切になると思います。
サッカーの場面でも、天候・ピッチ・味方や相手の状態まで含めて考えるクセがつけば、判断力はぐんと伸びていくはずです🙂
自分もサカパパとして、少しずつそうした声かけを試してみたいと感じました。
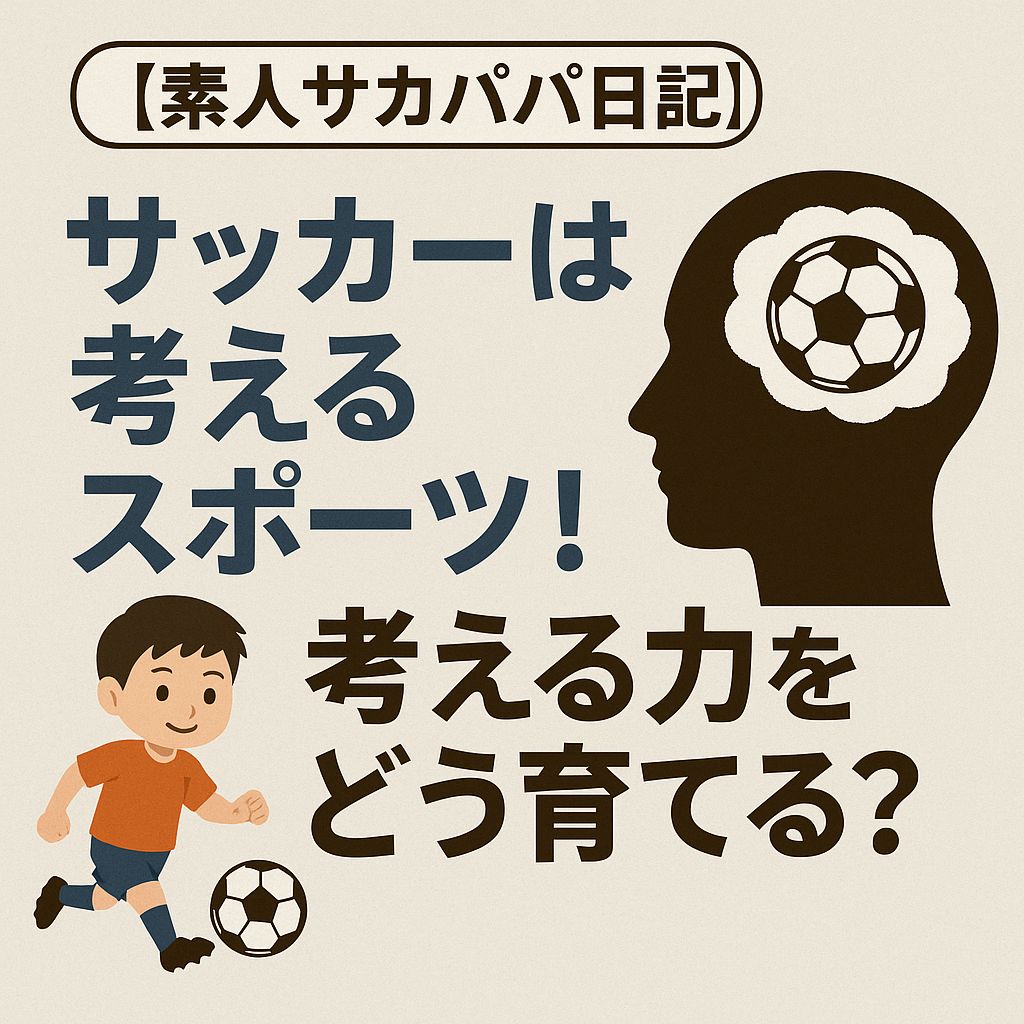


コメント