サッカーを始めたばかりの子どもたちって、なぜかボールに向かって一直線。
気づけば、みんなでボールを囲んでワチャワチャ…まるでサッカーじゃなくて「ボール取り合戦」みたいな光景に。
いわゆる“だんごサッカー”ですね。
うちのチームもまさにそんな感じでした。
でも、あるときから少しずつ広がりを意識してプレーできるようになってきたんです。
今回は、そんな“だんご状態”から抜け出すきっかけになった練習を紹介してみます。
■ コーチの「広がれ!」「幅!」の声が響く日々
練習を見ていてよく思ったのが、「なんでみんな、そんなに集まっちゃうの?」ということ。
サイドに立つ子に向かって、何度もコーチが「広がれ!」「幅!」と叫んでいたのが印象的でした。
たしかに子どもたちにとっては、ボールのある場所がすべて。
サイドでじっと待つよりも、ボールの近くで動きたくなるんでしょうね。だってボール触りたいでしょうから!
でも、それだとスペースはなくなるし、プレーも窮屈。
パスも出せず、蹴り合いになってしまう場面が何度もありました。
■ 4ゴールゲームで気づいたこと
そんな中で、よく行われていたのが「4ゴールゲーム」。
最初は、正直言って「これ、なんのためにやってるんだろう…?」とピンときませんでした。
でも、見ているうちに気づいたんです。
ゴールが四隅にあることで、自然と広がらないと点が取れない。
ボールが左右に動くたびに、子どもたちも自然とポジションを調整するようになっていきました。
このとき、
「あ、こうやって“幅を使う”ってことを体で覚えていくんだな」
と実感しました。
「広がったほうが、パスが通る」
「周りを見たほうが、味方が見つかる」
そんな“気づき”が、言葉じゃなく実際のプレーの中で少しずつ育っていったように感じます。
子どもたちも、スペースを使うようになってきたように思います。
■ だんご解消の別方法
本や動画で学んだのですが、
一定以上のパスをしたあとでないとシュートを打ってはいけない
とする特別なルールを使ったミニゲームも効果的なようです。
■ まとめ:楽しみながら“広がる”経験を
頭で理解するより、体で体験するほうがずっと早い。
「広がれ!」「幅を取れ!」と何度言われても、実感がないと動きにはつながりにくいですよね。
だからこそ、
「自然と広がらざるを得ない」ようなルールや仕掛けのある練習がとても効果的なんだと思います。

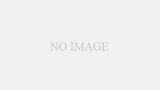

コメント