〜サカパパが感じたこと〜
はじめに
「リフティングって何回できる?」
日本のサッカー少年団ではよく耳にするフレーズです。
でも調べてみると、スペインでは少し違う捉え方をしているようです。
バルセロナの育成現場の声などを読むと、日本とは考え方にギャップがあることが分かりました。
スペインでは「遊び」や「感覚づくり」🎨
スペイン、とくにバルセロナの下部組織(カンテラ)では、リフティングを「回数」で評価する意識はほとんどないそうです。
- リフティングは遊びの延長
Facebookに掲載されたFCバルセロナ関係者の話によれば、スペインではリフティングの意識は日本に比べて非常に低く、コーチたちは「100回できるかどうか」よりも 楽しみながらボール感覚を養うこと を大切にしているとのことです【Facebook Futbol Para Ti 投稿, 2016】。 - 評価軸は“工夫”や“自由さ”
スペインの育成本や解説記事でも、リフティングは「遊び心」「創造性」を引き出す手段として紹介されることが多いです。部位を変えたり、友達と交互に続けたりといったバリエーションが重視されています。
つまり、リフティングはあくまで ボールを扱う感覚づくりの一つ であって、目標は「楽しみながら上達すること」なんですね。
日本では「回数=努力の証」📊
一方で日本では、リフティングは「何回できたか」を子どもや親が分かりやすい基準にすることが多い印象です。
- 「100回できたら一人前」と目標にしやすい。
- 宿題や自主練の定番。
- 達成感がはっきりしている。
これは悪いことではなく、モチベーションにつながる良さもあると思います。
プロ選手はなぜリフティングが上手い?✨
プロのアップを見ていると、みんな当たり前のようにリフティングが上手いですよね。
でも、彼らが子どもの頃に「回数だけ」をやり込んだわけではなさそうです。
- パスやトラップ、ドリブルの練習の積み重ねで自然に精度が上がっている。
- 幼少期から遊びの中で「ボールを落とさない感覚」を身につけてきた。
- だから、リフティングは「特別に練習した成果」ではなく「他の練習の結果としてできてしまう」部分が大きいのかもしれません。
素人サカパパ的まとめ👨👦
リフティングは確かに上達に役立つ練習。
ただ、スペインのように「遊び」「感覚づくり」として楽しむ視点も大切なのかなと思います。
日本式の「回数チャレンジ」はやる気を引き出しやすい。
スペイン式の「遊び感覚」は楽しさや創造性につながりやすい。
どちらも良さがあるので、うちでは…
「今日は30回チャレンジ!」
「次はサッカーテニスでもやろうか!」
と声をかけながら、両方のアプローチを取り入れるようにしていきたいです。
参考資料
- FCバルセロナ下部組織コーチの声:
「スペインではリフティングに対する意識は日本に比べてとても低い。100回やることよりも、遊びや感覚づくりを優先している」
(出典:Facebook Futbol Para Ti 投稿, 2016
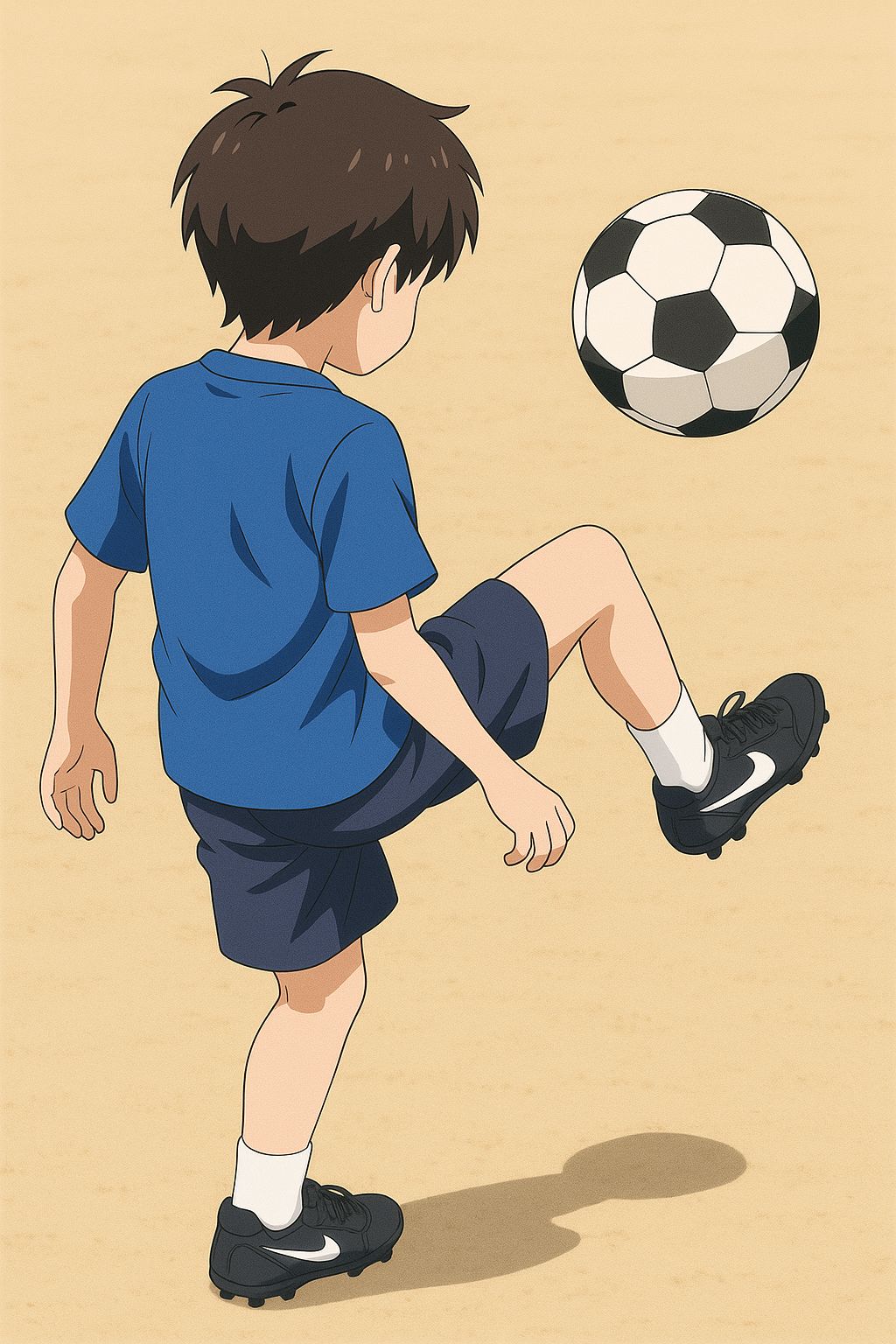


コメント